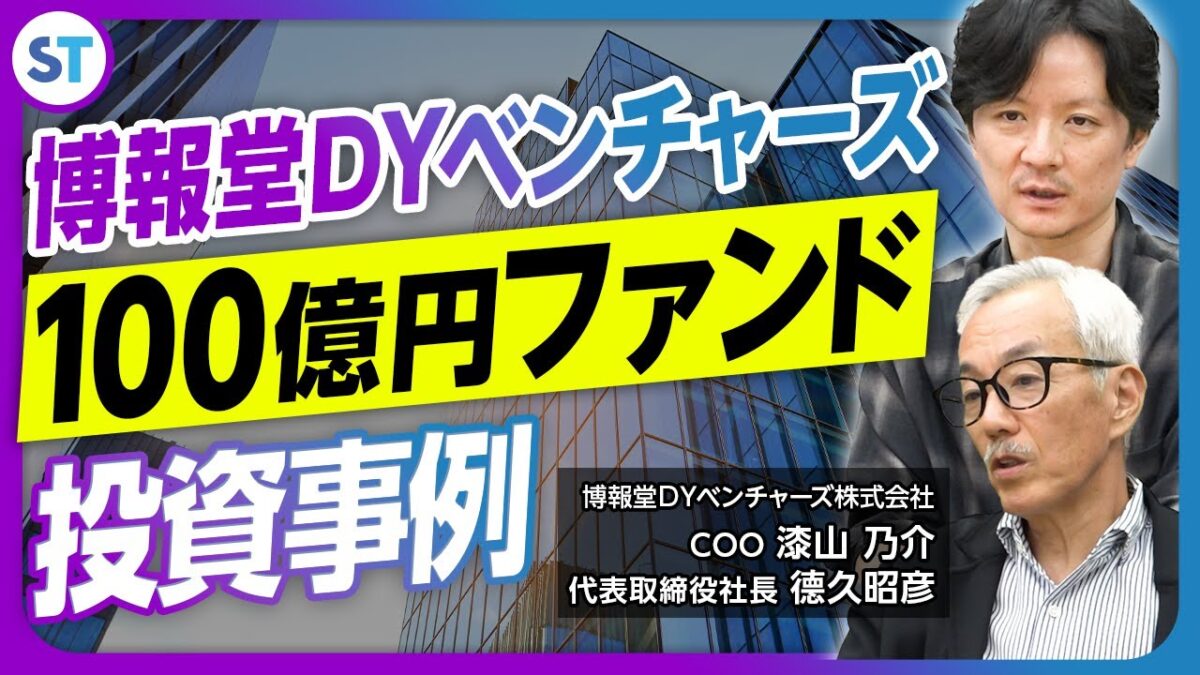100億円ファンドが投資したい企業の条件/成功・失敗事例を大公開【博報堂DYベンチャーズ 德久さん/漆山さん vol.01】
◯德久 昭彦 株式会社博報堂DYベンチャーズ 代表取締役社長
HP▶︎ https://www.hakuhodody-ventures.co.jp/
博報堂DYベンチャーズ代表取締役社長。
博報堂DYホールディングス常務執行役員を兼務し、社内企業プログラムVenture of Creativityを含む、博報堂DYグループのインキュベーション領域を担当。
以前はDAC(現Hakuhodo DY ONE)の専務取締役としてCTOやCMOを務め、アドテクノロジー領域の新規事業開発や国内外企業との資本業務提携投資などを推進し、日本広告業界におけるデータ活用や機械学習の導入や普及に尽力。
また、ユナイテッド(現任)やメンバーズといった上場企業の非常勤取締役を歴任し、デジタルやマーケティングを含め、さまざまな経営知見を提供。
◯漆山 乃介 株式会社博報堂DYベンチャーズ 取締役COO
HP▶︎ https://www.hakuhodody-ventures.co.jp/
博報堂DYグループにおいて、メディアビジネス開発やベンチャー投資を推進。
また、当社グループの社内ベンチャープログラムである「Ventures of Creativity」の選出委員として新規事業開発・立ち上げを支援。
当社グループへの参画以前は、ベンチャーキャピタルにてパートナーとしてベンチャー投資業務に従事。
それ以前には、大手人材サービス企業で複数の新規事業・サービス開発を経験。
石橋
はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資TV、GazelleCapitalの石橋です。今回からはですね、株式会社博報堂DYベンチャーズ、代表取締役の徳久さんと取締役COOの漆山さんに来ていただいておりますので、お二人とも今回からよろしくお願いします。
今日は改めてどういう背景を持って博報堂DYベンチャーズさんが立ち上がってきて、どういう規模でどういうところに投資しているみたいなところを色々とお伺いできればと思うんですけれども、まずはどういう背景があって博報堂DYベンチャーズさんが立ち上がってきたのかみたいなところを漆山さんから伺う方が良さそうですかね。
漆山
2019年から始まる中期経営計画の中で外部連携基盤の構築という、1つのテーマが打ち上げられました。端的に言いますと、オープンイノベーションの文脈の中で外部の、スタートアップだったりとか、一緒に連携しながら「新しいビジネスを作っていこう」という話がありまして、そこの中で、外部連携基盤の構築のための1つの、装置として、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)を、作ろうという話になりまして、始めたというところでございます。
石橋
博報堂DYベンチャーズさんができる前からスタートアップに投資とかM&Aなどは元々やっていらっしゃったんですか?
漆山
投資はもちろんしていました。博報堂DYグループで言うと、博報堂DYホールディングスもあれば、博報堂もあれば、メディアパートナーズもあれば、今博報堂DY ONEという名前になってますけども、DACだったりとか、それぞれでやっていましたというところがあるんですけども、スタートアップのM&Aっていうのは目立った例としてはなかったという風に思ってます。
石橋
作られてからファンド形式になられてるかなと思うんですけど、どのぐらいのファンドの規模感で、どういうチケットサイズで、CVCとしてやっていこうという感じで、約5年前からやってらっしゃると思うので、当時と今っていうところ、もし変化があればそれも合わせて教えていただければと思います。
漆山
2019年に始めた時にですね、100億円規模で、やってまいりましたと。
で、投資領域とかチケットサイズというところで言うと、設立当初はですね、いわゆる新しいビジネスモデルだったりとか、新しいテクノロジーのソーシングという目的で多様な領域を見ていくというところでやってきております。で、今70社ぐらいになってると。
チケットサイズは、100億のファンドっていうことになると、比較的その明確なチケットサイズを定めてやっていくっていうことが多かったりするかなっていうのはありますし、もしくはレイターステージになると、大きく踏み込むこともあったりするかなと思うんですけど、
基本的に僕らは、「機会をたくさん作りたい」という考え方でやってるので、1件あたりのポーションをめちゃくちゃ積んでやっていくっていうよりは、やはりその広く多様な新しいビジネスモデル、新しいテクノロジーを持っているスタートアップの方々と繋がっていきたいというところがありますので、チケットサイズでいうとそこまでばらつきがある感じではないですね。
石橋
徳久さんにも伺いたいんですけれども、どうしても博報堂DYベンチャーズっていう名前を見ていくと広告領域に投資をしていくのかなと思いがちですが、一方でポートフォリオ70社弱のホームページを拝見すると、多分これ関係ないんじゃねみたいなやつも結構なんか投資されてるんじゃないかなっていう勝手な印象を持ってるんですけど。今後特にどういうところとか、「こういうところもっと見ていかないとな」みたいなところってなんかお考えとかってありますか?
徳久
もちろん広告マーケティング領域っていうのはま、博報堂グループの本業ではあるという感じでございますけども、日本の歴史を遡ればベンチャーがグロースして大企業になっていくところをいろいろとサポートしてきたっていうことを考えた時に、今まさにやっぱスタートアップの方を日本の政府含めてですね、非常に大きく支援していこうというフェーズに来てるという。
ま、そんな中で広告マーケティング直接関係なくてもそういうところを我々って支援して成長をお手伝いしたいというところがありますんで、短期的にシナジーという意味では広告マーケティング領域ですけど、中長期的に考えたときはそれ以外のものも非常に重要と。
とはいえ、博報堂もクライアントさんであるわけですから、そこに役立つようなね、ソリューションをお持ちの方っていうのは当然あのしっかり見させていただくっていう感じでやってます。
石橋
博報堂DYベンチャーズさんに、ご出資いただいたスタートアップっていうのは何かどういうことを博報堂DYベンチャーズに期待していいというか、投資後のコミュニケーションであったりとか、特徴っていうところは、起業家の方はどう捉えておくと良さそうなのでしょうか?
漆山
ご期待は本当に多種多様っていうのがあるんですけども、最近はもう本当に起業家の方々もすごくよく理解してくださっていて、例えばデータの連携だったりとか、もしくは博報堂のお得意先様に向けて、一緒にソリューションを抱き合わせて一緒に提供していくとか、商流上の連携っていうのもあったりとかしますし、博報堂DYグループも非常にウイングが広いので、多様な連携が生まれてるというような状況ですね。
石橋
その上で、最も印象に残っている成功事例みたいなところですね。徳久さんからお願いしてもよろしいでしょうか?
徳久
そうですね、エグジットした会社は今のところ、我々2社ありまして、その1つに、クラダシっていう会社さんいらっしゃって、
商習慣上でですね、例えば飲料の賞味期限が6ヶ月で、小売に並ぶ時っていうのは製造されてから2ヶ月以上経ったやつっていうのはもう基本的に小売のお店に並べないっていう習慣がありますと。
まだまだ美味しく食べられるのに置くことができないと。ブランドさんからするとディスカウントストアで売るとことが基本的にブランドの毀損になってしまうので、下手すると破棄しなくてはいけなくなってしまうと。非常にこれはフードロスの課題に問題あるよねっていうことで、彼らそのクラダシさんはまだまだ美味しく食べられる食べ物とかを集めて生活者に提供すると。
その時に売るだけではなく、売ったうちの数%が寄付になるというスタイルを持ってるので、ブランドさんからするとブランドの毀損にもならないし、生活者さんも安いものをただ買ったっていうだけじゃなくて社会に貢献してるねっていうのを、みんなで感じる事ができるというサービスになってると。
ただですね、僕クラダシさんのことを、あるイベントでお会いするまで1ミリも知らなくて、たまたまのイベントのパーティーでですね、隣に座って、「何やってるんですか?」って聞いたところから始まったと。
ファンド作ってそういうこういろんなイベントに顔を出して、色々交流していくことで初めてできるっていう感じなんで、営業とか広告以外でもちゃんと協力できるっていうのが作れて、しかも出資させていただいてから1年半ぐらいで上場しちゃったんで。
こんなことがいつもあるとは思いませんけど、成功事例になったかなっていう風に思ってますっていう感じですね。
石橋
ありがとうございます。漆山さんいかがでしょう?
漆山
ジールスというスタートアップがありまして、そこはいわゆるチャットコマースのソリューションを提供しておりますと。1回検討フェーズにある生活者が購買に至らなかったんですけども、LINEのインターフェースに誘導していって、そこでコミュニケーションシナリオ設計して購買まで導いていくというような、こうチャットコマースのスタートアップさんがあるんですけども、
そこに関してはですね、マスからコンバージョンに近いところまでしっかりこう設計できるのかというところでいうと、組み合わせとしてはすごく相性も良くてですね、連携というところが非常にスムーズに進んで、いろんな得意先さんにそのソリューションを提供できているというところでいうと、組み合わせとしてはすごく相性がいいいいところがあったりしますね。
石橋
今ちょっと綺麗なところをお伺いできたかなと思うので、最大の失敗事例とか失敗体験みたいなところを是非お伺いできたらと思うんですがいかがでしょうか。
徳久
そうですね、基本的に経済的なファイナンシャルのリターンの話と、ストラテジックの話っていう両方あるんで、極論で言うとどっちか取れればいいっていうところありますと。
ファンドとしては独立して我々やってるので、このファンドが棄損していっちゃうっていう非常に困ると。このバランスをどうやって取るかっていうことかなっていう風に思ってます。
先ほどはご紹介してなかったですけど、カバーさんとか非常に大きくウィジットしていったところもあれば、
石橋
Vtuberですね。時価総額かなりつきましたもんね。
徳久
そうですね。で、すごくいいリターンを得ることができまして、CVCのランキングも我々が上がったりして非常に誇りに思っている案件なんですけれども、ただですね、あんまり社内で、「投資収益を上げました」と、いうことを変に主張するとですね、反感をかってしまうと。
ま、だから基本的に広告とかマーケティングをすることがやはり大事である。博報堂グループとしてはこのCVCって新しい取り組みなんで、それをいきなりこう投資的なスタンスで言い過ぎるとですね、「一体お前たちは僕らの何の役に立ってるんでしょうか」みたいなところが出てしまうので、先ほどのストラテジックとファイナンシャルのバランスっていうのがあったかなと思うんですけど、投資のめちゃくちゃな失敗っていうのは、漆山くん、もし記憶があればちょっとあの言ってもらいたいんだけど。
漆山
例えばD2Cみたいな、ビジネス領域が数年前にガッと来ましたと。ダイレクトに生活者と繋がってCRMとかしっかりしながら、直接ものを売っていくのはやっぱこう、マーケティング会社として非常に重要なんで、我々も投資目線でたくさん見てきましたというところがあります。
で、そこでいうとやっぱりうまくいったところもあれば、うまくいかなかったところっていうことで、そこは本当に学びがありましたね。どういう風な状況だとうまくいかないのか、どういう状況だとうまくいくのかっていうところが、
端的に言いますとやっぱり販管費のコントロールが適切でコントローラブルな状態なのかっていうと、あとはCRMですよね。やっぱり自分たちで、お客様と繋がるっていうことを継続的にやっていかないといけない。
このバランスがちゃんとできているかどうかっていうところの見極めがすごく大事だったなっていうところがあって、劇的にそこで何かめちゃくちゃ失敗したっていう訳ではないんですけども、モメンタムがすごいある領域で、その中でもやっぱりそのしっかり優勝劣敗みたいなのがこうちゃんと見えてくるんだなっていうところは非常ににラーニングがありましたっていうところです。
石橋
ちなみにD2Cと言われて久しくなってきまして、今後でいうとD2C見ていこうと思ったりされてますか?
漆山
いや、もうケースバイケースだとしか本当に言えないかなと思ってまして、科学はされてきてる部分もあるので、その中で「CRMをもっと頑強にできるような仕組みを持ちながらD2Cやっていくんです」とか、そういうところがあったりすれば、全然ケースバイケースなお話はしていきたいなと思うので、ま、D2C自体がもう全然ダメだよねとは全く思ってないですけど、そういう見極めがすごく大事だと思います。
徳久
そうですね、やっぱり基本的に物が溢れてるわけなんで、もともとある商品をD2Cで売り始めてもそれはやはりなかなか簡単に成功することはない。で、博報堂みたいな会社からすると、結局ブランド価値が上がったら利益が上がってくるというのはありますけど、安く売ってると、利益も少ないわけなんで、それずっと続けてるとやはりま、D2Cとして成長することが非常に困難と。
だからもともとブランドを持っている方がD2C作られるケースっていうのもありますけど、そういう方がある意味で超過収入が乗っかってくる形が作れるので、無名の方がD2Cブランドを作るってかなり厳しいと。
とはいえD2Cって物だけじゃなくて新しいサービスをダイレクトに提供するという強みもあるので、今までなかったような価値のあるサービスを作っていけばそれはどんどんブランド化していくっていうのもあるだろうなと思うので、その辺どうやっはまっていくかっていうのは我々ずっと注視をしてるという感じでございます。
石橋
博報堂DYベンチャーズさんだと、シード・プレシードみたいなラウンドではなくて、シリーズA前後とかが多いとは言えども、まずは投資したいと思える人の特徴とこういう人はちょっと投資するのが難しいかなと思う、逆に言うとちょっとネガティブなあのところの特徴みたいなものを是非お二人のそれぞれの観点でお伺いしたいと思ってるんですけど、徳久さん的にはいかがでしょう?
徳久
会ってみないと本当にわからないですし、我々チームは結構丁寧に直接会わせていただいたり、ヒヤリングとかインタビュー重ねるっていうのが結構我々すごくやってはいるんですけども、その中でやっぱり起業家の「何を成し遂げたいか」っていうかな、やっぱその思いは非常に大事だなと思ってます。
最初からね、そこがクリアな人っていうのはそうそういないと思うんで、やっぱり色々チャレンジしていく中で、すごくしっかりその自分が世の中に提供したいことっていうのははっきりしてる方はやっぱりすごくいいなと思う。
ま、それが途中でね、ビジネスモデルが変わったり、ちょっとサービスの領域が少し変わったりとか、そういうのはしょうがないので、そういうパーパスにちゃんと合ってるかっていうのがですね、わかって行けばすごく投資したいなっていう風に思います。
石橋
漆山さんいかがでしょう?
漆山
そうですね、なんて言うんでしょうね、パターンって全くないなって思ってて、
ただ自分なりに見つけてきたペインみたいなものを、めちゃくちゃ楽しそうに伝えてくれる人っていうのはやっぱり巻き込まれますし、魅力的だなと思いますし、どんなに小さくてもいいんで、「いやこれ僕ずっとやってきたんですけど、ペインだと思うんですよね」みたいなことを言ってくれる人が、まずはやっぱりすごく魅力的だなと思いますね。
石橋
今40後半ぐらい投資先がいるんですけど、1社2社しか学生起業家のいないんですよ。今おっしゃっていただいたみたいな、ガーッとやっていって、お仕事やっていったからこのペインが見えてきてとかっていう経験が、もしかしたら学生起業家のって相対的に少ない可能性が高いじゃないですか?
そういう中だと何か漆山さんとしてもやっぱなかなか若い起業家、学生起業家のってなかなか投資実際難しいなとかって思われたりしますか?
漆山
いや、そこは結構課題かもしれないですね。僕らが逆にできてないところなのかもなと思っていまして。
徳久
ま、でも社会人経験があまりない方も(投資先に)いますね。
石橋
必ずしも経験が浅いからダメというわけでもない。
漆山
そうですね、はい。
徳久
ま、スタートアップ3年やったらね、大企業に10年いるよりいい経験できるケースは多分あるんで、「3年苦労してここか」っていう経験っていうのはやっぱり結構説得力ありますよね。
石橋
最後にですね、今後、博報堂DYベンチャーズさんとして成し遂げたいこととか達成したいことを是非お伺いして締めていければと思いますので、メッセージお願いしてもよろしいでしょうか?
漆山
博報堂DYベンチャーズも、ファンドとして5年っていうことで、他もね、長い歴史を持たれてるファンドさんもいらっしゃいますし、CVCとしてもね、まだまだあの足りないところがいっぱいあるなと思ってます。
基本的に、博報堂DYグループっていうのはですね、人肌を持って接する人間が非常に多いグループですので、そこをウザいと言わずに楽しんでいただけるようなベンチャーで、なおかつ我々としても非常に共感できるようなパーパスを持って作りたい世界観が一致すればですね、非常に大きいシナジーが作れるんじゃないかなと思ってますんで、我こそはっていう方はお声かけください。
石橋
それでは改めてお二人とも最後までご出演ありがとうございました。
徳久
ありがとうございました。
石橋
次回は、お二方がそもそもどういうご経歴でCVCを立ち上げて今に至ってらっしゃるのかみたいなところ中心にお伺いしてまいります。
なぜ大手博報堂DYグループのベンチャーキャピタルの社長になれたのか/知られざる経歴と働いて感じたギャップを語る【博報堂DYベンチャーズ 德久さん/漆山さん vol.02】
石橋
はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資TV、GazelleCapitalの石橋です。
今回ですね、前回に引き続きまして株式会社博報堂DYベンチャーズ、代表取締役社長の徳久さんと取締役COOでいらっしゃる漆山さんに来ていただいておりますので、お2人とも今回よろしくお願いします。
徳久&漆山
よろしくお願いします。
石橋
前回、第1回目の配信ではお2人から博報堂DYベンチャーズさんとしての、投資活動の全体感とか、こういう成功事例あるよねみたいなところを色々具体的に伺いましたが、そもそもお2人が誰なんだみたいなところは第1弾では完全に割愛させていただいてたので、第2弾ではこれから投資を受けようと思ってる起業家の方が、こういう人たちなんだなってことが伝わるような温度感のあるお話を伺えればと思いまが、
徳久さんから何かどういうご経歴なのかっていうところ、博報堂DYベンチャーズの社長に選ばれたっていうことは、何か金融畑でずっと長くお仕事されてたからこそそのポジションで抜擢されたみたいな感じだったんでしょうか?
徳久
いや、全くそんなことはなくてですね。博報堂っていうのは、広告マーケティングをやる会社なので、基本的に金融専門の人間っていうのは、ほぼほぼいないっていう会社ですね。そこで2001年に、インターネット広告をやってた先輩がいて、まあそこで「お前も来い」と言われまして、ネット広告やるベンチャー企業に入りました。行ったところで大変だけど楽しいなっていうのを経験しましたと。
石橋
それがDACですね。
徳久
そうですね。DACですね。その中で、いわゆるアドテックっていうやつが、2011年ぐらいからどんどん成長していくわけなんで、そこの事業開発をどんどんやっていこうっていうことで、単純にあの僕も広告を理解してるだけだと面白くないので、新しく広告を売る仕組みだったり、より効果を上げる仕組みだったり、そういうのを作るのに興味が持てたので、そこをどんどんやっていこうっていうことでやってましたと。
まあ中でも特に、アメリカの方が非常にやっぱりデジタルマーケティングで進んでたので、アメリカのアドテックの会社を色々研究をして、それで年に数回は、まあシリコンバレーとか、シアトルとか、ニューヨークとかに行ってですね。
例えば年間100社ぐらいはあって、そのうちの数社に例えばじゃあ一緒に事業提携をして日本にこのテクノロジーを持ってこよう。我々が販売代理店的に付き合うっていうのもありますし、じゃあ日本向けのカスタマイズに関して僕らは金をだそうと。
それで日本向けにそのサービスをアジャストしてやりましょうとかですね。あるいは、ある程度こうたくさん売ってくださいっていうのを彼らが言ってくるんで、まあその代わりにじゃあコミットメントするよりもっていうことで、投資させていただく。そこから、あなたの成長をやってくれればいいよみたいな形で、投資と事業開発をこう合わせてやるっていうことを十何年やってきましたと。で、それはそれで非常に楽しかったんですけれども。
2018年にDACが博報堂DYホールディングスに買収されまして、完全子会社になりました。私としては上場も経験しましたし、TOB(株式公開買付)もされるということも経験しましたと。
その中でたまたま漆山とか頑張ってですね、CVCを創ろうっていうところで、僕があのベンチャーキャピタリストになりたいと言ったわけではないんですけど、元々そういうベンチャーさんと協業すること投資することもあったんで、割とすんなりこの役目をやらせてもらってるという感じでですかね。
石橋
徳久さんの場合はTOBになって博報堂グループに来たけれども、漆山さんの場合はかなり前からいらっしゃったんですか?
漆山
僕は博報堂DYグループに来たのは2017年からなんで、それ以前はもう全然違うバックボーンになってまして。
僕ですね、金融の経験と言うよりはどっちかというと事業会社での経験というところで、一番長くいたのはその人材とか情報サービス系の、非常にもう既に大きくなってしまった会社でメディアの開発とか制作的な業務だったりとか、そっから派生してサービス開発とか事業開発JVを作る、とかそういうことを現場側で、もうガリガリガリガリやってたっていうことをやってまして、まあそれも非常に楽しいなということでやってました。
ただその会社ですね、35歳になると、退職金が非常に上増しされてですね、出るか出ないかを考えるタイミングなんですね。
そこで色んなVCさんに相談して、その中で言われたのが、「そんなに色々興味あるんだったらVCの方が色々見えるよ」っていう話の中で、「そうか」と、ハッとなる部分もあって、当時大学院にも通ってて、大学院にもたまたまなんですけど、VC出身の先生の方がいらっしゃったんですね。
っていう背景もあって、リクルートを辞めて前職のVCファームに転身しましたというような流れがありました。
石橋
当時何年にVC業界って入ってらっしゃったんでしょうか?
漆山
2015年からですね。
石橋
どのタイミングでジョインしたんですか?
漆山
博報堂DYグループに来たのは2017年の4月ですね。
石橋
なんでDY行こうってなったんですか?
漆山
自分でファンドの立ち上げみたいなのを、前職のVCファームにいる時に見させてもらって、それを自分でやっぱりやってみたいっていうのがありまして、その中でやっぱり博報堂DYグループでもCVCを立ち上げようとしてるぞっていう話がありましたので、チャレンジしてみたというところでございます。
石橋
2017年に来られてから約2年間ぐらい想像通りの計画だったそれとも何か思ったよりめちゃくちゃ苦労したんですか?
漆山
全く想像通りではなくてですね、自分の力量不足もありましてなかなか時間もかかってしまったというところがありまして、大体2年間ぐらいかけて社内で色々悪戦苦闘しながらっていうところですね。
石橋
ここからちょっと是非お2人の関係性みたいなところ伺っていこうかと思うんですけど。
僕も、CVCを前職クルーズという会社でやってたんですけど、社長はお前じゃないだろうみたいなことをフィードバックをいただき、社長は辞めるリスクが少ないやつで親会社の社長が、CVCの代表を兼任したという格好で僕らの場合はあの決着したんですけど。
博報堂DYベンチャーズさんの場合はどういう流れでなんでその徳久さんだよねっていう風に選ばれたんですか?
漆山
それは正直僕にもわからないですね。わからないっていうのが正直なところなんですけど、ただ海外に行って年間100社とかのスタートアップに会うとほとんどもうそれVCがやってる仕事なんで、そういうことをやってる人っていうのがもうほぼいないっていう話なんで、選択肢は他に無かったんじゃないかなという風には思いますね。
石橋
徳久さんからしても急に来たんですか?そういうCVCで代表やろうみたいな。
徳久
TOBが決まってからCVC作るからって言われて、それまで全く知りませんでした。
いや、ただ当然そのTOBされた後、自分のキャリアも当然考えるタイミングでありますよね。そんな中でベンチャーキャピタルっていう仕事が僕にもできるのかっていうことで、それはもう二つ返事でした。だからでもただ自分で考えてたわけではないと。
石橋
当時で言うとVCではなかったわけじゃないですか。その上でイメージと違うところとか、いいポイントも悪いポイントも何かどちらも、どんな感じのイメージなんですか?
徳久
元々そのDACで投資した時、やはり事業連携的なシナジーがあるっていうのが前提のところしか基本的には投資してなかったですし、そういう意味で今この博報堂DYベンチャーズっていうのは、いきなりそのシナジーがあるわけじゃないっていうで中長期的にはあるよねっていうことで非常に広いこう産業を見てるんですね。
でその時に違う視点でやっぱ見れるようになったっていうのがすごく大きいし、逆に言うと、その広告マーケティングのスタートアップさんだと、元々自分がやってたことなんで、逆に「本当にそれでうまくいくの?」みたいな、ある意味で専門家の罠というか、ジレンマに陥ってしまうみたいなところがあるので。
そこをどう見るかっていうのはちょっと面白いですし、こんなに勉強になると思わなかったですね。
石橋
漆山さんはCVCの準備には時間かかったお話でしたけど、やっぱこういうところも課題あるなとか、やっぱこういうところはギャップだったなってところってあられるんですか?
漆山
どちらかというと僕は新しく事業を作っていくとか、そういうことに関して周りがサポーティブな環境でずっと生きてきたっていうのがあって、CVCっていうのはやっぱりこのある種、緩衝地帯というか、出島的なところなんで、我々の博報堂DYグループの仲間とスタートアップのカルチャーっていうのって、みんなこれ言葉で言うのは簡単なんですけど、いかにこうスタートアップフレンドリーになるかってめちゃくちゃやっぱ難しいんですね。
やっぱり日々接してる人じゃないと中々わかんないっていうのはありますんで、そこをより意識的に丁寧にやらないとグループの中におけるCVCの役割をなかなか果たしきれない部分もあるなという風には思っててんで、スタートアップと接してる中で僕らが感じてることみたいなものをグループの仲間とも共有しながら、そこをしっかりブリッジしていきたいなっていう思いはより強くなってきてるというのはあります。
石橋
是非、博報堂DYベンチャーズのチームの皆さんも会社のチームメンバーサイトですかね、のところにもあの記載がございますので、ご連絡取ってみたいなと思う方はURLの方からお問い合わせいただければと思ってます。
それではお2人とも第2弾もご出演ありがとうございます。
徳久&漆山
ありがとうございます。
【100億円ファンド】博報堂DYベンチャーズはどこへ向かうのか/現在の取り組みと今後の展望【博報堂DYベンチャーズ 德久さん/漆山さん vol.03】
石橋
はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資TV、GazelleCapitalの石橋です。
今回はですね、1弾2弾に引き続き、株式会社博報堂DYベンチャーズ代表取締役社長の徳久さんと取締役COOの漆山さんにご出演いただいておりますので、今回もよろしくお願いします。
徳久&漆山
よろしくお願いします。
石橋
第1弾の動画では改めて博報堂DYベンチャーズさんの、CVCとしての投資活動みたいなところ、第2弾の方は、今VCやってて今後どういうところやっていきたいねみたいなところを伺ってまいりましたが、第3弾目は今までCVCやってきたからこそ博報堂DYグループ今後どういうところにCVCの取り組みを、進化させていくのか、徳久さんからぜひちょっとシェアをいただきたいんですけれども、お願いしてもよろしいでしょうか?
徳久
はい。博報堂DYホールディングスっていう持ち株会社がありまして、そこの直下にこの博報堂DYベンチャーズっていう、CVCがございます。オープンイノベーションを進めようっていうのは5年前の新中期経営計画で博報堂DYグループとして決めた話ではあるんですけども、やはり5年前とはですね、グループの状況も変わってきてますと。
というのもありますし、広告マーケティング業界的にもですね、プラットフォーマーの存在が非常に大きくなってきて、業界が大きく変わっていったっていうところがりますと。
他にもですね、産学連携でしたり、大企業さんといろいろJVを作ってやっていこうっていう動きだったり、社内で起業をするプログラムみたいなものを作ったりと、さまざまやっています。
そういうものを連携させていこうという、私はその立場も持ってるんで、新しい事業開発をやってる人たちとどうやってうまく連携してシナジーを発揮できないかという取り組みがだんだん形になってきたかなっていう感じでございます。
もちろん、そのオープンイノベーションっていうのは、スタートアップさんだけやってれば済む話ではないという事ですし、社員の立場でもまあ事業作りたいという人もいますし、あるいはある程度株も持ってですね、博報堂DYが親会社であるっていう状態で作りたいっていうような姿勢として、Ventures of Creativity株式会社っていうのがですね、2024年から始めておりまして。
みんながスタートアップやれるわけでもないですし、とはいえ、単純に今までの事業部門で新しい事業を作ろうと思ってもそれはなかなかですね、旧来的な関係に引っ張られてしまうんで、そこでどうやってこう遠心力と求心力のバランスを取るかっていうところを、様々な仕組みを作りながら、今試してるという感じで、それがだんだんと、社内にとって見ても、だいぶ整理がついてきて、
やっぱり世の中の変化も非常に激しいので、AとBとCのパターンがあればいいねっていう形では、もう今やどんな大企業さんでも通用しない。それを柔軟に組み合わせていかないといけないというのが、今の想いとしてあります。
石橋
例えば、CVC以外のそういう企業促進系の取り組みだと何かどんなプレイヤーの方とどんな取り組みやってるみたいなところ、どんなイメージになるのでしょうか?
徳久
東大IPCが参画するWE ATというのがありますけど、こちらは、東大IPCさんとミライの事業室、ここがメインで協力している所で、博報堂以外の大企業とも協力しながら、スタートアップを盛り上げていこうとか、あるいは大学発の技術を活かすような場面を作っていくっていうようなところもありますで、そういう試みっていうのも始まってていう感じなんで。
で、あとはHakuhodo JV Studioなんてのもありますけど、これは割と大企業同士をこう結びつけていこうみたいなところでやったりしてる部分で、そこに一部スタートアップの技術を絡めていこうみたいなところもやってますし、
あとquantumっていうのが、割とディープテックにフォーカスしてまして、ここはもうハンドオンでやっていかないとなかなかビジネス化がしづらいんで。まあ当然そういうハンドオンでやっていくとたくさんの社数ができないので、我々の投資先をquantumがやってる仕組みはめるのか、あるいはquantum自身で投資をするのかみたいなことを、いろいろ話し合いながらやってますと。
そうじゃないと、ディープテックってやっぱ時間もかかるんで、普通の投資家だとずっとこう黙って5年10年見守るっていう感じになってしまうんで、まあそれだけじゃないビジネス開発っていうのもあるのかなっていうことで、我々としてチャレンジさせていただいてるっていうことで、どんどん時代と我々の状況に合わせて整備していくのが、我々の今の状況ということになりますと。
CVCというのは、一番スタートアップと会えるので、そういう意味では色々なところに繋がりやすいかなということでやっております。
石橋
やっぱりCVCという取り組み単体では、親会社さんとかグループとか事業会社さん側の事業開発ニーズってのはCVC単体で満たすっていうのはなかなかやっぱ難しいんですね。だからこそこういう取り組みが増えてきてるっていう感じなんでしょうか?
漆山
もちろんその、米国が全て正解だとは思わないんですけども、いわゆるこのコーポレートデベロップメントとか、コーポレートベンチャリングっていうのをすごく立体的に捉えて、もちろんアクセラからM&Aみたいなこう手法は役割が違うんで、違う人とかが見ていくっていうのあると思うんですけども、戦うための1つの手法や手段っていうのをひと揃えながらやっていくっていうのはすごく重要だと思ってますんで、その過程に各社さんあって思考錯誤っていうのが、引き続き続いているのかなとは思ってるというところですかね。はい。
石橋
漆山さんからキーワードとして出てきたM&Aっていうのも徳久さん目線でも博報堂グループとしてはスタートアップM&Aも強化していくっていうイメージで認識正しいのでしょうか?
徳久
広告マーケティングという産業でいうと、スケールさせるのが意外と難しい。
博報堂グループの中に入った方がいいよねっていう風に意思をお持ちなのであれば、お声かけくださいっていう感じですし、私自身も、上場も経験しましたし、TOBも経験した事からすると。
いろんなやり方ありますっていうことで、IPOだけが必ずしもイグジットではないっていうのはもう身をもって体験してますし、TOBされた後もですね、僕がいろいろ仲良くしてる、超大企業のCEOがいるんですけど、彼なんかどんどん買収をして、その買収した先のコアメンバーを自分のこう戦略を作るメンバーにどんどん入れてっているんですね。
それによってますまグループのビジネスがスケールする、それがどんどんこう普通の世の中になってきてることを考えた時には、M&Aっていうのも、事業作っていったり、スケールさせていく上で非常に重要なあのやり方だと思うので、そこはあのフラットな目線で考えていただければなと思いますし、我々も常に上場だけが出口ではないっていう風に思ってますという感じでございます。
石橋
博報堂グループ入りしようしまいみたいなところでご関心ある方は見ていただいてる方も多くいらっしゃると思いますので、お問い合わせフォーム等からご連絡いただくのも良いかと思いますが、業界イベントにもお二人ともいらっしゃってることが多くあるかと思いますのでぜひ突撃していただいて名刺交換いただくと、その後出資関係とか資本関係のきっかけにもなっていくかなと思いますので、このお二人の顔見かけたらお声かけいただければ良いのかなと思っております。
それでは改めて、お二方、第3弾まで最後までご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。
徳久&漆山
ありがとうございました。