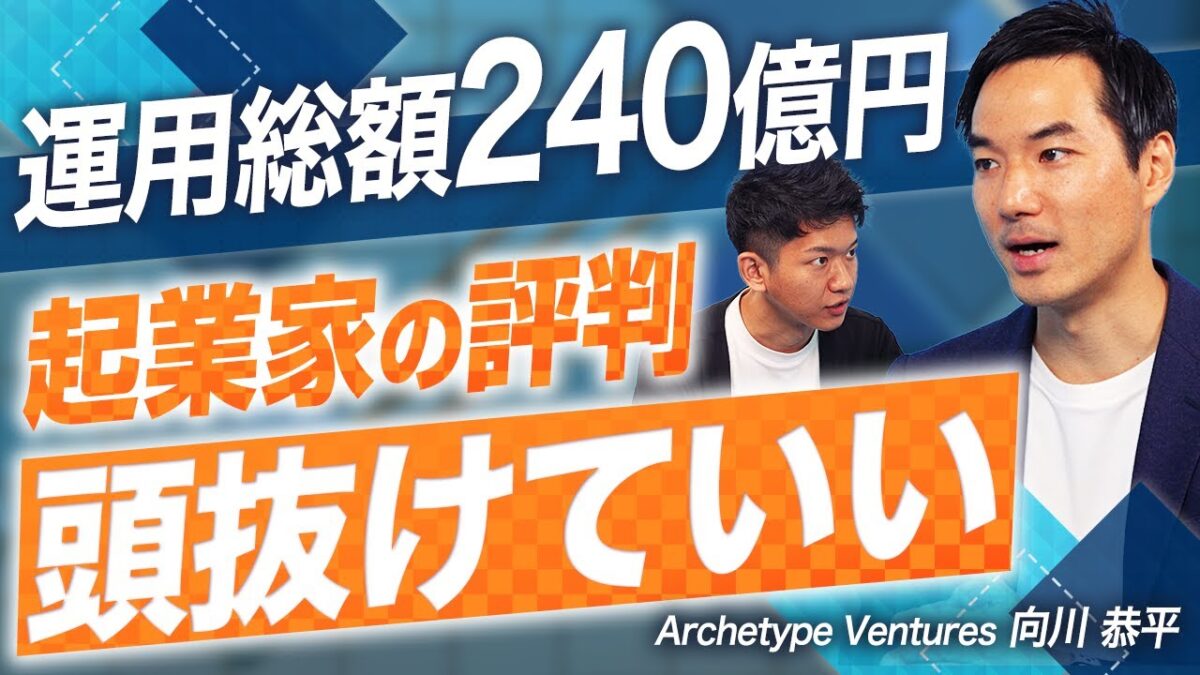【起業家からの圧倒的支持】BtoBスタートアップに注目するVCが語る”本当に投資したい起業家像”【Archetype Ventures 向川 恭平 vol.01】
◯向川 恭平 Archetype Ventures パートナー
公式HP▶︎https://archetype.vc/
3号ファンドより福井・中嶋と共にGeneral Partner(GP)を務める。
新卒三菱商事にて国内外の上下水道事業を含むインフラ事業に従事後、 日米クロスボーダーVC DNX Venturesを経てArchetype Venturesに参画。
UC Berkeley Haas School of Business MBA修士(Class of 2018)、東京大学経済学部卒。
高校生起業インキュベーションプログラム「Blast! School」アドバイザー。
石橋
皆さんこんにちは、スタートアップ投資TV、GazelleCapitalの石橋です。今回は、なかなかメディア露出しないことで有名というのも変ですが、Archetype Ventures パートナーの向川恭平さんにご登壇いただきますので、よろしくお願いいたします。
向川
よろしくお願いします。
石橋
今回、冒頭でもちょっと軽く触れさせていただきましたが、Archetype Venturesさん、略してアーキさんで僕呼んでしまうんですが、アーキさんあんまりメディア露出、積極的にはされてらっしゃらないですよね。
向川
そうですね。創業が2013年なんですけども、これまで代表の福井も中嶋も、ほとんど特にこういう動画系のメディアは出たこともなくて。出たことがあったとしても、起業家さんとの対談記事とか、そういったところでメンバーが記事として出てくるっていうことはありますが。今回お招きいただきましてありがとうございます。
石橋
ありがとうございます。むしろご視聴いただいて非常にありがたいなと思うところなので、せっかくなのでこの動画さえ見れば、Archetype Venturesさんから出資を受けたいとか、投資検討してもらいたいなっていう起業家さんが「全て、もうArchetype Venturesの全て分かったぞ」っていう動画に、せっかく出ていただいたが故に仕上げていきたいと思いますので、しっかり向川さんにお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。
向川
よろしくお願いします。
石橋
早速なんですけれども、まずちょっと大きい単位のところからというか、まずは向川さんのご説明をちょろっとだけいただければと思ってまして。そもそも今パートナーでいらっしゃると思いますが、どういうご経歴でどういう経緯で今のArchetype Venturesさんのパートナーとしてコミットメントされてるかっていうところをお伺いしても大丈夫ですか。
向川
はい、分かりました。僕は新卒は三菱商事で、水道ですとか下水道のインフラ系の事業をずっとやってまして、海外で民営化されてるプロジェクトに出資をしたり、国内でいろんな浄水場の運転管理を引き受けて、民営化の提案を市長さんとか水道局長さんにしていくってことをやっていたので、ちょっとだいぶ今とは世界観が違うところにおりました。
石橋
だいぶどころではないぐらい違うところに。
向川
そうですね。本当に現場の水道施設の関係者といかに仲良くなるかっていうようなことばっかり考えたりはしてたんですけども。そこからUCバークレーにMBA留学を行く機会っていうのがあって、当然サンフランシスコの近くではあるので、もう会う人達っていうのがもう起業家でありVCでありっていうところで。
やっぱりこの5年10年のスパンで、人々の生活をまるっと技術を使って変えていけるっていうところに、もう完全に感化されたというところで、それでこの業界に入ってきましたっていうところですね。 卒業した後に、DNXベンチャーズという、これまた日米のクロスボーダーのVCで3年半ぐらいですかね、おりまして。その後自分で独立をしようと思って。
石橋
そうなんですね。
向川
DNXを辞めた後に、そうなんです、そうなんです。色々模索をしていたんですが、そのタイミングでたまたま、僕がそのDNXにいた時によく共同投資していた福井も、新しいファンドをこれから立ち上げるというところだったので、声かけしてもらって参加したという形になってます。
石橋
へえ。最近、足元でもう去年ぐらいからかな、1号ファンドとして独立される方すごく増えてるような所感を僕自身も思ってるんですけど、向川さんとしてはどうしてそのタイミングで独立をされようとしてらっしゃったんですか。
向川
いくつかあるんですけども、1つはVCの事業って非常に長いじゃないですか。特に我々みたいなアーリーステージですと、起業家さんに出資をしてからっていう時に、僕自身もやっぱりこう作っていきたいそのファンドのあり方とか、そういったものっていうのを少しこう大切にしていきたい部分っていうのもあって。非常にVCとしての仕事が楽しかったからこそ、自分の島でやっていくことが良いのかなっていう風に思ったからっていうのが一番大きいかもしれないですね。
石橋
逆にその中で、そこの思想があられながらも、福井さんたちというかArchetype Venturesさんとしてやっていこうっていうのは、何が決め手だったんですか。
向川
ありがとうございます。1つ、かっこいいことばっかり言ってもしょうがないので、1つ時代というか状況みたいなとこで言うと、僕がその独立の思考してたのって2022年の頭前後だったんですよね。ですので、あのタイミングってSaaSのマーケットがクラッシュして、やっぱりこう起業家のみならず、いろんなVCが本当にこう資金調達に苦労してっていう時期だったので。僕自身が自分であの独立をしたところで、なかなかちょっとお金が集めにくい部分あるんだろうなっていうような、そういったとこっていうのはもちろんありますが。
福井ないしはアーキタイプのメンバーとはっていうところなんですけど、やっぱりこう起業家に対するこう向き合い方というか。ご存知だと思うんですけど、福井を。
ある意味親友みたいになるじゃないですけども、やっぱりこうどんな苦労してる時でもこう寄り添う、最後まで一緒に戦い抜くっていう、そこの部分がやっぱりすごく共感できたっていうのが一番大きくて。僕自身も、こんなファンドにしていきたいなっていう思いの、かなりそこに近いところがあったんですよね。
ですので、そこがすり合えば、自分で始めようが、元々僕が参加するまでに10年近くですかね、会社としてはあったとしても、これからまだまだ第2創業っていう方はあれですけども、参画して会社を大きくしていける余地があるんじゃないかなと思って、はい。
石橋
でも、まさになんだろう、僕が確かにいいことばっか言ってもしょうがないのかもしれないですけど、この後この動画の中では「どういうVCさんなんだ、Archetype Venturesさんは」ってお話するわけですけど。その説明する前の段階にこんなこと言うとあれですけど、多分Archetype Venturesさんの投資先の起業家の方からの評判っていうのが、図抜けていいVCファンドさんの代表格って言っても、全然メディア露出はしてないんですけど。
いわゆるビハインド・ザ・アントレプレナーっていうべきなんでしたっけ。要は起業家の方が目立つべきであり、投資家は目立つべきではないよねという思想がとても強いVCさんだし、それが故なのか、投資先の方とか起業家の方への向き合い方とか温度感みたいなところはめちゃめちゃ高いからこそ、結果、起業家の方からの評判がすごくいいVCさんなのかなとは。
何社さんかご一緒させていただいてるとか拝見してても、今ちょっと向川さんじゃなく、福井さんの話になっちゃいますけど、量あるキャピタリストとしての、もちろんGPとしての福井さんで立場もあれば、キャピタリストとしての福井さんっていう関わり方はこういう人なんだなってのはむちゃくちゃ伝わるので。
向川
うん。彼自身も元起業家というところで、やっぱりそこの起業家さんに対するリスペクトとか、彼らが1番表に立つべきであるっていうところは、すごく思想として強く持ってますし、そこはうちのメンバーみんなが共有してる部分かなっていう風には思います。
石橋
是非ちょっと知っていただくためにも色々ブレイクダウンして聞いていければと思うんですが。今ちょっと流れで、福井さん福井さんって名前だけ言っちゃってるんで、改めてパートナー陣の方々の簡単なご紹介と、是非チームのメンバーの方々はどんなところいらっしゃるってところを、ちょっと向川さんからご説明いただいてもいいですか。
向川
ありがとうございます。我々は今、フロントとバック含めて11人のチームではあるんですけども、創業GPという意味では中嶋と福井というメンバーが、本当に2014年から立ち上げたファンドになってます。 僕が今回の3号ファンドで参加し、新しいGPという風な形になっていて。で、プラスアルファもう1人パートナーという北原というメンバーがいるというところが、まずそのGP、GPパートナークラスっていう風なところですね。
中嶋はもう今年還暦って言っちゃったら怒られちゃうかもしれないですけども、かなりの大御所ではありまして。それこそ電通で新規事業ですとか、そういったことをずっとやった後にですね、Microsoftの初代の社長の、成毛さんが社長やってらっしゃったインスパイアという、大企業向けの新規事業コンサルティングとかスタートアップへの投資をやっていた会社の副社長まで1回務めまして。
その後、我々の資本関係のない姉妹会社ではあるんですけども、アーキタイプというですね、これもスタートアップ投資と大企業向けの新規事業コンサルティングっていうのを、当時本当に2006年ですので。まだまだもう、スタートアップするにしても会社を設立するのが大変、ファンドでお金を出資受けるのが大変っていうところで、コワーキングスペースを提供したりしていきながら、本当にこう初期の起業家を支援するっていうのを彼が始めていて。
その繋がりで2013年にArchetype Venturesっていうのが立ち上がったんですけども。福井は福井で、元々NTTデータ出身で、彼は2年ぐらいですかね、自分で起業して、割とクイックにその事業っていうのをイグジットして。その資金でアメリカに留学をして、また第2の事業をやろうとしてるタイミングで中嶋と会ってベンチャーズを作ったという風な形になってます。
石橋
いい意味でハードな巻き込まれ方をしたみたいなところは、なんか福井さんがよく飲んでる席とかでお話しいただくので、面白い形で創業されていったんだなと感じつつなんですが。 他のメンバーの方で言うと、どういうご経歴の方とかが多いのかなっていうのは。なんでかというと、以前ですね、この番組にトリビューの毛さんがご出演をいただいたことがありまして。元々毛さんはArchetype Venturesなのかな?アーキタイプ側なのかな?
向川
アーキタイプの方、コンサルの方ですね。
石橋
にご在職されてる時に、いわゆるEIR(アントレプレナー・イン・レジデンス)かな、の、要は起業家を志しているんだが、一旦VC側の中にいるみたいな、そういった立ち位置でご在職されていらっしゃったみたいなことを以前の動画でお話しいただいたので。EIRも含めていろんな方いらっしゃるのかなってイメージがあるんですけど、実際どんなもんで、ベンチャーズ側やってらっしゃる。
向川
はい、ありがとうございます。先ほど、まず中嶋と福井の話で言うと、やっぱり2人とも自分で起業してるっていう経験を積んでるファンドというところが、多分僕らの1番の特徴かなっていう風に思ってまして。事業を作っていきたいっていうメンバーが結構集まっているというところと、1つの画一的なやり方を持ってるというよりは、本当に幅広いバックグラウンドのメンバーを集めているっていうのが、我々のチームかなという風に思ってまして。 例えばですけども、まず総務省から、例えば北原で言うと、総務省から留学を経てBCGに行って、福井とここも元々留学時代の知り合いっていうところであの参画をしてくれていたりですとか。
あとは、伊能さんっていうメンバーは、MICINっていう遠隔医療の初期社員みたいな形で、彼女自身もかなりスタートアップでの経験を持っていたりですとか。 あとは中村君っていうメンバーがいるんですけども、彼は野村證券でずっと金融のことをやってたバックグラウンド。
先ほどEIRって話がありましたけども、実は今、現役の起業家も2名、投資業務には関わってもらってまして。あの野村美紀さんという方は、我々の1号ファンドの支援先のグロース・パートナーであった、日本のカントリーマネージャーではあったんですが。その後キャピタリストを長らくやった後に、今は自分であの食の…
石橋
そうですよね。
向川
アメリカに日本の調味料を売っていくというスタートアップをやっていきながら、農業ですとか食の領域のスタートアップに投資してますし。あと、物部さんっていう、こちらも元々1号ファンドの支援先の、お医者さんがいるんですけども。彼も今自分の事業っていうのを持ちながら、デジタルヘルスケアですとかそういった領域に特化をして、投資業務ですとかバリューアップのをやってるっていうところで。 本当にいろんなバックグラウンドの人たち、特にその事業を作ってくのが好きなメンバーっていうので構成されている部分かなという風に思います。
石橋
すげえ。野村さんは多分同級生で、割とOrigamiさんの時代に、学生じゃないかな、の、長期インターンの面接かなんか受けに行った時になんかであの、当時の野村さんと繋がって。で、気がついたらアーキタイプさんにいらっしゃって、僕もなんかよく分かんないけど気がついたらVCにいるわけですけど。 結果的に今僕も、食べ物系のお酒系のところでもう一社事業会社をやってるので。
向川
そうですね。LocalLocalですよね。
石橋
そうです、そうです。情報交換みたいのをさせていただいたりとか。で、まさになんか、起業にチャレンジされてる方とか、起業経験に近いご経歴の方々が多いんだなってのは、今改めてご整理いただいて、すごく理解できたので。 先ほどちょっと触れさせていただいたような、起業家さんに近いというか、思い持ってサポートされるというか、一緒にやっていくみたいな方が多いっていうのは、創業メンバーのお二方の思想とか思考っていうのが強く影響してるのかなってのは、すごい。
向川
そうですね。やっぱり僕らも、その起業家さんが普段味わってるそのヒリヒリ感って、頭では理解してるつもりなんですけど。やっぱりあの野村美紀さんとかって、自分のそのキャッシュフローマネジメントとかで日々アクセクしていたりは、もちろん当然起業家なのでされていて。 なんかそういうのが、例えば我々の社内定例ですとか、そういった場で、やっぱりその、そういった立ち位置にいらっしゃる方が近くにいるっていうのは、やっぱりこう、そういった気持ちを忘れないようにするって意味においては重要かなっていう風には僕も思います。
石橋
理解です、ありがとうございます。ちょっとチームのところのお話とか、背景のところはだいぶ分かってきたので。あえて、もうちょっと、多分起業家の方が気になるところというか、ちょっと数字面回りとか、投資活動の概要もお伺いしていければと思うんですが。 大体1社に対して、累計いくらぐらいまでを基本投資していくような方針で、どういうラウンドで、リードなのかフォローなのかとか、どういう市場に投資するんだみたいなところ、ちょっと基本的な概要のところいただいても大丈夫ですか。
向川
あ、もちろんです、ありがとうございます。3号ファンドという括りで言うと、今155億のファンドを、去年の10月にファイナルクローズをいたしまして。メインファンドで言うと、2014年に起業していて、1号10億、2号60億。ちょっと順番が前後しちゃいましたけれども、そんな形でこう、やってきてるファンドになっています。
石橋
トータル220億程度ぐらいを運用してるって感じですか。
向川
そうですね。1つ、追加投資用のファンドみたいなものもあって、累計では240億ぐらい、はい、あの、やってるんですけど。いわゆるメインファンドっていうところで言うと、はい、まさにそれぐらいの規模になって。
石橋
逆にじゃあ3号ファンドはズドンと大きくなった感じなんですね。
向川
そうですね。1号から2号が6倍で、2号から3号が2.5倍ぐらいっていう風な形になってますが。社数ベースで言うとそこまで実は増えていなくてですね。1号が22社、2号が22社、そして3号が、今回155億っていうのを大体30から40ぐらいの間で投資しようとしてまして。1件あたりの支援先に対する投資額っていうのを、しっかり増やして応援していきたいっていう、そんな形のコンセプトになってます。
僕らは、BtoB領域に基本的には特化をしたVCというところで。これBtoBって言うと非常に幅広いと思うんですけども、起業家さんが作られているプロダクトが法人向けに売られてるというところであれば、基本的にはこう、エンタープライズソフトウェアである必要があるとか、そういったことも全くなくてですね。まずはBtoBですと。
その中でも、投資をする領域としては、大企業向けのものももちろんありますし、バーティカル、産業特化型のものを提供してるところもありますし。ビジネスモデルとしても、SaaS、AIみたいなものも当然あるんですけども、最近は結構ディープテック領域ですとか、サステナビリティですとか、デジタルヘルスケアみたいなものとか。あとはバイオテックの会社なんかにも投資をしたりしてきてますので。本当にそこは特に3号ファンドになってから、少しずつこう領域は広くなってるかなという風に思います。
チェックサイズとステージの話で申し上げますと、我々、大体こう初回のチェックというのが、プロダクトがあって売上のモメンタムがまだそんなに出ていない、我々は「Seed Plus ステージ」っていう方をしてるんですけども、あえて。自分たちのポジションを取ってるので。世間一般で言うと、シードとシリーズAの間という風な形ですね。
このタイミングで大体5000万円から1.5億円ぐらいの間で初回こう、投資させていただきます。その後当然、イグジットに向かってシリーズA、Bって続いていくわけですけども、会社の伸びに応じて、1社あたり大体5から7億、最大10億ぐらいこう追加投資をしていくっていうような、だいぶフロントヘビーな一応ストラテジーっていうのを取ってまして。
石橋
間違いない。
向川
はい。そんな思想で大体30社から40社ぐらい投資をしていこうという風な考え方であってます。
石橋
なるほどですね。非常に、もうシンプルで分かりやすいんですが。もうそうなると、基本はリード投資が全てっていう感じになるんですか。
向川
そうですよね。必ずしもそこはこだわってないっていうのが、僕らの特徴かもしれないですね。今、結果、1号2号はやっぱりそのファンドサイズの制約もあって、リードできてる会社ってのはそんなに多くはないんですけど。一応、社外取とかに入ってる会社もちろんあるんですが、多くないんですが。 福井がよく言ってたのが、「僕は常に心のリードになる」っていう言い方を彼はしていて。それも僕ら、ある意味ちょっと、なんて言うんですかね、モットーみたいにはなってるんですけども。出資額に関わらず、全力で起業家さんに、リードをしてるかのごとく向き合っていこうっていうのは、あるんですけども。
3号ファンドで言うと、結果的に今はだいぶ、ほとんどと言っても過言ではないぐらいリードって形になってるんですけど。
ただこれって、やっぱりこう起業家さんによって、ものすごく資金需要が必要なので、シリーズAでやっぱり大きなファンドを入れておきたいとか、いろんなことって多分あると思いますし。 僕らの場合は、そのシード投資だけとか、そのシリーズAだけっていうわけではなく、シードプラスから結構長く見ていけるっていうところがあるので。どっかのラウンドでしっかりとリードを取っていければいいかなっていう風に思っているっていうところですね。
なので、もちろんリード、我々がタームシートをして、取締役を派遣してっていうような形になれば、それに越したことはないと思いますけれども、そこに必ずしもこだわってるわけではないっていうスタンスですね。
石橋
理解です、ありがとうございます。ちなみに、投資をいただいた後のコミュニケーションだと、先ほども僕の方からも触れておいてなんですけど、投資先の起業家の方からの評判がどうでもいいってなると、関わり方にももしかしたら特徴があるのかなと思ったりもするんですが。どういうご支援だとかサポートをされることが多かったりするんでしょうか。
向川
ありがとうございます。この辺のハンズオンの話って、多分どのVCさんもやってらっしゃいますし、全てがうまくいってるわけではないので、頑張ろうとしているっていう多分文脈でしかないと思うんですけど。できる限り僕らとしては、もうやれることをやっていきたいっていう思いはあって。その意味でもチームのバックグラウンドを多様化してるんですよね。 なんで、HRのエキスパートがいたり、金融系のエキスパートがいたり、コンサルがいたり、事業開発ができたり。僕なんか、元々生まれがアメリカで。
石橋
生まれアメリカなんですね。
向川
そうなんですよ。なんで、10歳ぐらいまでアメリカに住んでたので。例えば海外の投資家さんとこうやり取りをしたいっていう時に、起業家さん側に入ってデューデリをこう支援したりするっていうのこともあったりするんですけど。 本当にそういうパッケージとして、アクセラレーターをやりますとか、そういうものはあんまり持ってないんですけども。個人として提供できる、例えばこう採用ですとか、あと大企業とこう繋いでいくみたいな部分に関しては、中嶋がやっぱりそれなりにすごく長い業歴があるですとか。
僕とか福井とか北原も、起業家さんだけではなくて、色々な企業さんと関係を作っていこうとしてますので。この採用、いろんな顧客紹介ですよね、みたいなところですとか。あとはもう本当に事業計画、その戦略の壁打ち含めて、担当なんかもこう入れ替わっていきながら、その時々のお困り事に応じてメンバーがついて支援をしてくってようなことをやっています。
石橋
ちょっと動画の第2弾の方でもう少し踏み込んで、なんで投資したのシリーズみたいなところで、向川さんが実際に3号ファンドとしてご出資されてるところの具体面もお伺いしていくと思うんですが。 今、1号、2号、3号の話を伺う中で、そんなにいっぱい社数投資しないっていうのは理解できたんですね。となると、投資したい起業家ってなんか特徴があったりですとか、こういう属性の人みたいな。
これもちろん、向川さん個人のというよりかは、Archetype Ventures社として、こういう人とやっぱり探していかないといけないよね、みたいななんかあるのかなと思ったりするんですけど。 そういう、こういう起業家に投資したいみたいな、Archetype Ventures目線で何かあったりしますか。
向川
ありがとうございます。これもなんか僕らの特徴なんですけど、結構やっぱりみんな、応援したい起業家の像ってそれぞれポジションが明確に違っていたりして。これも良しかなっていう風には思うっていう前提があるんですけど。
ただ、チームとしてやっぱり共通してるのは、解決するその課題の社会的な意義っていうものが大きいかどうかっていうところは、我々としても非常に意識をしてるところで。で、これが必ずしも別に、インパクトとかそういう話は全くないんですけども、解決することであの社会が豊かになるのかとか、そういった、これって解決する意味があるんだっけっていうところは、結構チームとしては非常にこだわってるかなという風には思いますね。
石橋
はい。いくつかそのArchetype Venturesさんとしての、代表的なその流れでの投資先の事例ですとか、イグジット事例みたいなところもお伺いできればと思いますが、事例としてあげるとどういうところなんでしょうか。
向川
ありがとうございます。イグジットで、だいぶ大きくなってきてるっていうところで言うと、2023年ですかね、に上場したABEJA(アベジャ)っていう会社ですね。創業が多分2012年とかだと思うんですけども、マシンラーニングですとか、機械学習の本当に黎明期に立ち上がった会社さんで。 当時、岡田さんは結構リテール向けにいろんなAIソリューションなんかを提供していて。今はもう本当にAIのデジタルプラットフォームっていう形で、LLMなんかを独自で作られてると思うんですけども、そこが大きく上場したという事例かなと思いますね。
あとは、物流のDXをやっているHacobuさんですね。物流管理ですとか、やってる会社さんですけども。トラックのバース予約とか、配車管理とか、そういった会社ですとか。 あとは、FLUXとか、テックタッチさんとかですかね。
FLUXさんは、もう今AIを生かして大企業向けにいろんなソリューションを提供してる会社になってますけども。当初は、パブリッシャーというか、メディアを持っている会社さん向けに、いわゆる広告枠の収益の最大化をしてくようなソリューションを提供していて。今は本当にAIに根付いたソリューションっていうのも、大企業向けに提供してるっていう風な会社になってますし。
あとテックタッチさんは、デジタルアダプションプラットフォームと言いますか。SaaSを例えば大企業で導入されて、どうやって使っていいか全くわからないで、みんな情シスとかITサポートに電話をかけて、ただオンボーディングができないっていう課題っていうのを、サーズの上に彼らが作っているサーズっていうのをレイヤーすることによって、ある程度使えるようになるっていうような会社さんとかかなという風に思います。
石橋
先ほど向川さんから、Seed Plusで、それも若干ポジショニングも含めて、というようなお話もいただきましたけど。155億円のサイズでやっていらっしゃる場合によっては、一旦一般論で言うと、アーリーとかシリーズA、B前後っていうところも出資されるケースも当然あられると思ってまして。 そうすると、競合VCじゃないですけど、要はかち合っちゃったりとか、いい企業さんによったらどっちが選ばれるんだみたいなところでの取り合いみたいなところも当然あるかとは思います。シードでも当然あるので。
そんな時に、そのArchetype Venturesさんとしての、改めて特徴とか強み、要は起業家さんが僕らを選ぶべき理由みたいなところを、是非お伝えをいただければと思うんですけど。どんなところが、起業家さん目線に立つとアーキさん選ぶべきっていうところなんですかね。
向川
はい、ありがとうございます。これあれですね、自分語りをするなっていうファンドからすると、1番苦しい質問だと思うんですけども。
石橋
とんでもないです。
向川
いや、そうですね。ただ、僕らがやっぱり1番経験値を積んでるというところで言うと、やっぱりこの、プロダクトがあって売上のモメンタムがあんまりない時期って、1番苦しいタイミングだと思うんですよね。 特にBtoB領域の場合って、ある程度プロダクトができたとしても、売れるようになるまでの時間かかっちゃうじゃないですか。なので皆さんこう、シードで調達をして、大きなお兄さんたちが待っているそのシリーズAに行くまでの間に、だいぶこう、キーマンの採用もしなきゃいけないし、シグネチャーロゴって言いますか、やっぱりいい会社さんに入ってもらわなきゃいけないってとこで皆さん苦労されると思うんですけど。
我々は本当に、福井を中心としてそこでずっと戦ってきてるVCではあるので。その中でこう一緒に、我々が、本当に営業から採用からやってくっていうスタンスを取ってますので。そのステージにいらっしゃる方っていうのは、すごくやっぱり相性がいいんじゃないかなっていう風に思うところですかね。
石橋
改めて最後に、是非Archetype Venturesさんとして、目指してこういうことを成し遂げていきたいよねってところを、ちょっと起業家さん目線にメッセージをいただければと思うので、最後お願いしてもよろしいですか。
向川
ありがとうございます。我々は、投資家、当たり前なんですけど、投資家という風な形ではあるんですが、起業家さんとこう一緒に伴走していきたいっていう風な思いを持ってるVCですし。そういう意味では、もう本当にこう定例会含めてですね、かなりこう中にしっかりと入って議論していきたい。それで非常にこう大きなソリューション、大きな社会課題を一緒に解決していきたいと思ってますんで、是非よろしくお願いいたします。
石橋
ありがとうございます。 第二弾では、向川さんが出資された会社について、なんで投資したんだっけということを聞いていこうと思いますので、よろしくお願いします。
向川
よろしくお願いします。
【なぜ投資した?】240億円VCが語る投資を決断した理由|広い領域に注目する投資戦略とは【Archetype Ventures 向川 恭平 vol.02】
石橋
皆さんこんにちは、スターアップ投資TVの石橋です。今回も、前回に引き続きましてArchetype Venturesの向川さんにご出演をいただきますので、今回もよろしくお願いいたします。
向川 よろしくお願いします。
石橋
今回はズバリ「なんで投資したのシリーズ」としまして、アーキタイプベンチャーズさん、向川さんたちが実際に出資をされた起業家に、なぜ当時投資の意思決定ができたのかというところを具体的にお伺いしながら、皆さんがどういう風な投資の見立てをされるのかとか、伴って起業家の皆さんにはアーキタイプベンチャーズさんがどういう起業家さんに投資をしたいのかというところを、しっかりご理解いただくためのコンテンツにしていければと思っておりますので、今回もよろしくお願いいたします。
向川 よろしくお願いします。
石橋
もしかしたら具体に踏み込みすぎて、後からカットになってるかもしれないので、今回はいくつかの起業家さんについて取り上げていきたいなと思ってるんですけれども。
(深掘りしすぎたため1社目は割愛)
石橋
2社目についてもお伺いできればと思いますが、2社目の方の社名、代表名、事業概要をサクッといただいてもよろしいでしょうか。
向川
ありがとうございます。2社目はALYという会社ですね。中澤さんという方がCEOをやってらっしゃる会社です。この会社は何をやってるかと言うと、病院向けのソリューションでして、電子カルテと接続をして、電子カルテの情報を元に、お医者さんが作らなきゃいけないドキュメンテーションってめっちゃ多いと思うんですけど、紹介状ですとか主治医意見書、まあとはお医者さんだけではなくて、リハビリスタッフさんとかがいらっしゃって。そういうサマリーですとか、あとは退院する時の退院看護サマリー、こういったものを過去の診療歴から自動的に全部作ってくれるっていうようなサービスを作っている会社になります。
石橋
よりバーティカルなソリューションというか、業界特化型ってところだと思うんですが、元々中澤さん、創業者の方のご経歴が、その医療バックグラウンドみたいな感じの方なんですか。
向川
これが面白くてですね、今ではチームとして徐々にそういう専門家っていうのも集まってきてはいるんですけど。実は彼もUCバークレーなんですよね、たまたま。
石橋
そうなんだ。
向川
それだけで投資しているわけではもちろん無くたまたまなんですが。中澤さんは元々エンジニアですね。元々AI insideのチーフサイエンスオフィサーというか、データサイエンスを仕切ってたメンバーですね。 そこを経て自分で起業して、いろんなデータサイエンスとかAIって言ったものを社会実装した時に、最もその価値がある領域ってどこだろうって彼自身が考えた結果、医療はもちろんそうですし、今ご存知の通りお医者さんってすごく過労働の問題があって。今、医療改革の一環でお医者さんの労働問題っていうのは結構上がってく中で、少しでもこの業務を効率化して、医療行為以外の業務を減らしていきたいっていうところで、ここの領域を選ばれたという風な会社さんですね。
石橋
じゃあ元々はこの医療業界の中にいたっていうわけではなかったって方だったんです。
向川
ではないですね、はい。
石橋
ちなみに先ほど、元々MBA時代にみたいなお話もありましたけど、出会ったのもその頃からで、ずっと壁打ちをしてらっしゃったって感じだったんですか。
向川
いえ、行ってるタイミングが多分被ってなくて、たまたま同じようなロケーションにいたっていうだけなんですけども。出会いは、第1弾でもお話をした物部ですね。彼がやっぱり医療系のスタートアップの中でかなりネットワークがあって。
石橋
なるほど。
向川
で、一方であの、デジタルヘルスというよりは、もう少し結構病院にがっつりこう入り込んでいくようなサービスでしたので、そこはじゃあ一緒にやってこうっていう形で。どちらかというと、その投資の判断っていうところは僕がもう入らせてもらってやったっていう形なので、出会いは本当に物部経由でっていう形になります。
石橋
EIR制度、ソーシングでめちゃ機能する説あるかもしれない。
向川
そうですね。
石橋
やっぱり起業家さんの周りには起業家さんいらっしゃいますもんね。
向川
そうですね、そう思います。
石橋
ありがとうございます。是非、向川さんたちが投資意思決定した背景みたいなところも、ALYさんについてもお伺いできればと思いますが。 まだ、出資した時点ではシードプラスぐらいだったんですか。どれぐらいの感じだった。
向川
いやもう、今言っていただいた通り本当にシードプラスのステージだったなという風に思います。やっぱりこの特に医療業界の、特にこの本丸の病院のその基幹システムに接続するって、多分この領域で長らく投資されてる方々からしても、ちょっと及び腰になってしまうようなものかなっていう風に思うんですよね。
どちらかというと、周辺の問診ですとか、クラウドで少し、院内システムと接続するというよりは外側でっていうところが多かったのかなっていう風には思うんですが。
我々としては、改革っていうんですかね、やっぱりどの病院もしっかりとある程度効率化をしていって。今のこの国費のこの医療負担の問題もありますし、サステナブルな労働の問題っていうところで、結構病院さん側が、セキュリティっていうのはすごく大切に強化していれば、こういったものに需要してくるような世の中になってくるんじゃないかなっていうのが仮説としてはありまして。
それで投資したというところと、中澤さんの会社自体、先ほど言ったそのチーフデータサイエンティストオフィサーって言いましたけども、経営チームの中にやっぱりこうセキュリティのスペシャリストとか、かなり、そのエンジニアが作った組織だからこそ、そのセキュリティですとか、サービスに対するアーキテクチャーの作り方がかなりしっかりしてるっていうところがチームとしてはあって。この会社だったら受け入れてもらえるんじゃないかなっていうところがあって、はい、投資したという形になってます。
石橋
いい意味で色合いの違うBtoBの、とはいえソフトウェア系とかAI系のところの2社さんだったのかなという振り返りなんですが。アーキさんの3号ファンドって必ずしもソフトウェア系のBtoBだけじゃないとは思うんですけれども、他のテーマとか他の領域の3社目の方の事例とかってございますか。
向川
そうですね。例えばですけども、カルタさんっていう会社がありまして。こちらはですね、またもうだいぶ毛色が違うと思うんですけども、園芸作物の高速品種改良に強みを持ってる会社ですね。
石橋
全然違いますね。
向川
今具体的に何をやってるかと言うと、今イチゴの品種改良をしてまして。日本のイチゴってもう世界に冠たる美味しさというものがあるかなっていう風に思うんですけども。ただこれって、日本のその気候帯にあったものなので、世界中どこ持ってっても、バーティカルファーミングでもしない限りは作れないっていうものがあるんですけども。
カルタさんの場合は、これまで例えば県の研究センターとかが10年かけて品種改良してきたものを、2、3年で改良していけるっていう強みがありまして。で、かつその業界を見ると、もちろんその品種改良してるプレイヤー、生産者さん、小売さんって、これは全部プレイヤーさんが別々という中で、彼らのチームっていうのは、研究開発から販売まで一気通貫でやろうとしてるので。そこの消費地の近いところの気候帯っていうのを理解していきながら、高速で品種改良するっていうのをやってまして。
これは海外だけの話ではなくて、日本もやっぱりどんどん気候が熱くなってきていて、夏のフルーツなんかでもちょっと栽培ができなかったり、味が落ちたりっていうケースで色々あると思うんですけど、そこにも資するような品種改良っていうのをしていくっていう会社に投資をしています。
石橋
だから場合によっては、カルタさんは、今挙げていただいた事例に限って申し上げれば、ちょっと違うカテゴリーの、バイオ系っていうんですかね、領域のスタートアップなのかなと思うんですが、こういうところでも全然投資検討は積極的にできるし、前向きに投資もしてこうっていう方針でらっしゃるんですよね。
向川
ありがとうございます。そうですね。ファンド、例えばこれ3号ファンドで全部投資終わった後のポートフォリオを見た時には、おそらくBtoBの、大企業向けのソリューションとか、バーティカルのソリューションっていうのが、比較的過半数以上というか大半にはなるだろうなとは思うんですけども、積極的にそういった会社さんの投資もしてますし。
本来であれば多分第1弾でお話すべきだと思うんですけど、僕らのその投資検討の1つの特徴としては、できる限りそのお客さん、ポテンシャルのお客さんとか、現状のお客さんのヒアリングっていうのも非常にこう大切にするっていうところで。
我々自身がその専門性がない分野に関しては、やっぱりあの方々の話っていうのを、とにかく聞きに行くっていうことをしてますので。そこでやっぱりニーズとか、他のスタートアップとの立ち位置でスタンドアウトしてるなって感じる部分があれば、積極的に投資してくっていう風なスタンスになってます。
石橋
なるほどですね、ありがとうございます。ちなみにちょっと一瞬ぐーっとまた話を戻しちゃうご質問になっちゃうんですが、こういったバイオ系だと、先ほどまでのそのソフトウェア系の、今回例えばシードプラスで投資させていただいたとして、シリーズA、Bに向かうためのマイルストーンとか、どういうKPI設定、またちょっと色合いが違うのかなと思うんですが。向川さんたちとしては、CULTAさんになんかどういうポテンシャルを改めて感じて、どういう仮説を作れたからこそ、今回のラウンドでご出資できたっていう。
向川
CULTAさんに関する僕の理解で言うと、ニーズは自明だったんですよ。僕がアメリカに留学してる時も、本当にフルーツちょっと「うーん」って感じでしたし、やっぱりインバウンドで来られる方も「日本のフルーツ最高じゃん」って皆さん言うじゃないですか。
僕も出張とかでシンガポールとか香港とか行っても、やっぱりかなり高い、日本のイチゴは。で、少しこう品質が落ちてる部分で、韓国産とかオーストラリア産とかってのがこうあってく中で、ここに日本のイチゴ持ってけたら絶対売れるよねっていうところは、もう間違いないだろうなっていうところがありまして。
やっぱり技術の部分なんですけど、CLUTAさんの場合は、いわゆる創薬ベンチャーとかのように、ここで1つの新しく発見した薬がとか、1つの技術がっていうよりは、もう少しオペレーション全体の話なんですよね。その品種改良してく上での、本当にもういろんなステップがこうあるわけじゃないですか。
改良したものも、実際に作ってみる時にどんな肥料を使ってくかとか、そういったものとかって色々チューニングしてかなきゃいけないと思うんですけど、そこはやっぱりオペレーションのエクセレンスみたいなところで担保できるとこっていうのもすごくいっぱいあったので。必ずしも100%サイエンスリスクを負ってるわけではないっていう風な判断の仕方もできたので。
そういった意味では、ニーズは明確ですし、何かしらこう、いわゆるディープテックっぽいようなサイエンスリスクを過度に負ってるわけでもないだろうなっていう風に思ったというところと。 野秋さんって、起業家が、ビジネスとサイエンス両方とものすごく感度が高い方なので。で、やっぱり農業分野で見ると、起業家さんいらっしゃっても、彼みたいな人はやっぱり稀有だなって覚えたので、っていうところですね。
石橋
今回は複数社取り上げていただいたわけですけれども、やはり全体として、実際シードプラス、早めの段階からご出資をされてるからこそ、多分取り上げていただいた会社さんも、現時点でVC・スタートアップ界隈でみんな知ってるよね、というか、これから大きくなるチャレンジをされていくようなフェーズからご一緒されて、しっかりご支援入られてるっていうところが、まさになんかアーキタイプベンチャーズのやり方というか、方針なんだろうなっていうのは、具体のお話からもすごく伝わりました。
ちなみになんかゴリゴリのプレシードはさすがに触らないって感じになるんですか。
向川
でも、できればそれぐらいから会話をさせていただきたいなと思ってまして。やっぱりこのシード、プレシード、プレシリーズAぐらいって、そのやろうとしてる事業から逆算した時の調達金額、起業家さんの特性によってみんな結構バラバラじゃないですか。 で、僕らがこのシードプラスにこだわってる理由って、起業家さんと信頼関係を築いて、いろんなご支援をしてくっていうところも、正直、会社が大きくなりすぎると、もういい会社って優秀な人って採用できちゃってるので。
それより前に人間関係をちゃんと作って、我々としてご支援できることをしていくってことをしないと、単純にキャピリストとしてやってる面白みっていうのはないですし、起業家さんにもあんまり貢献できた気にも個人的にはちょっとならないっていうところが、うちのアーキタイプベンチャーズがこの領域にこだわってるっていうところなので。
必ずしも早ければ投資できないってことでもないですし、逆にグロースステージでも、例えば全く新しい領域に出てくとか、そういうところで0→1を一緒にこうやってかなきゃいけないっていうところであれば、もちろんご相談には乗れるかなっていう風に思うので。あんまりこう画一的に、シードプラス以外は見ませんっていうわけでは全くないです。
石橋
はい、了解です。是非、あえて多分シードプラスというところが分かりやすくはあるとは思います。
向川
そうですね、そこがメインではあります、もちろんですね。
石橋
幅広く、これ見ていただいてる起業家の方、相対的には創業期の方の方が多いのかなとは思いますので、是非アーキタイプさんにコンタクトしてみていただいて、早めからお話をしてみていただくと。結果的にご縁が作りやすいのはシードプラス、少し物が出始めて、みたいなフェーズかも分かりませんが。 是非、なかなか表に出てくるVCさんではないですが、本当にリスペクトするべきベンチャーキャピタルさんなのかなと思っておりますので、ご連絡見ていただければなと思います。それでは第2弾に渡りまして向川さん、ご出演ありがとうございます。
向川
ありがとうございました。